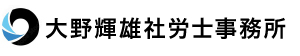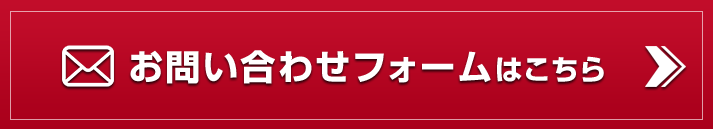「来年もまた賃上げが必要か…」
「うちは体力的に厳しいけど、やらないと人が来ない」
――今、多くの中小企業の経営者の方が、そんなジレンマを抱えているのではないでしょうか。
先日、経済同友会が2026年の賃上げに関するアンケート結果を発表しました。それによると、回答企業の68%以上が賃上げを「実施予定」で、全体平均の賃上げ率は4.05%になる見通しだそうです。大企業を中心としたこの賃上げの流れは、もはや「他人事」ではありません。なぜなら、賃上げをしないと優秀な社員が辞めてしまったり、新しい人材が採用できなくなったりするからです。この記事では、この「賃上げ時代」に中小企業が取るべき給与戦略について、経営者が考えるべき3つの対策を分かりやすく解説します。
なぜ今、中小企業も賃上げを避けて通れないのか?
経済同友会の調査では、製造業で4.26%、非製造業で3.95%と、業種を問わず高い水準の賃上げが予測されています。この流れは、人手不足が深刻な中小企業にとって、大きなプレッシャーとなります。
1. 優秀な人材流出を防ぐ「防波堤」としての賃金
大企業が高い賃上げ率を示すと、中小企業で働く社員は「このままでいいのだろうか」と感じやすくなります。結果として、スキルを持った優秀な社員が、より高い給与を求めて大企業や競合他社へ転職してしまうリスクが高まるのです。
賃上げは、社員の生活を支えるだけでなく、自社の優秀な人材を守る「防波堤」として機能します。
2. 「採用力」を維持するための必須条件
今の求職者は、給与水準を非常に重視しています。「少しでも高い給与」を提示できる会社に人が集まるのは自然なことです。
大企業が4%を超える賃上げを実施する中で、賃上げを見送ることは、採用市場において「給与の低い会社」という印象を与えかねません。企業が安定して成長していくためには、賃上げは「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えるべきでしょう。
賃上げ時代に中小企業が考えるべき3つの対策
体力に限りがある中小企業が、ただ漫然と給与を上げるだけでは、経営を圧迫してしまいます。賢く、効果的に賃上げを行うための3つの対策をご紹介します。
対策1:全員一律の賃上げではなく「メリハリ」をつける
大企業のような一律のベースアップ(基本給の引き上げ)は、中小企業にとって大きな負担になります。そこで、給与を上げる対象や額に「メリハリ」をつけることが重要です。
- 評価と連動させる:頑張って成果を出した社員や、高いスキルを持つ社員に重点的に給与を反映させましょう。これにより、社員のモチベーションも向上します。
- 特定の職種に絞る:特に人手不足が深刻な部門や、会社の利益に直結する専門職(例えばITエンジニアなど)に絞って、市場価値を反映した高い給与水準を設定することも有効です。
「誰に、何を期待して給与を上げるのか」を明確にすることが大切です。
対策2:賃上げだけでなく「福利厚生」で魅力を高める
給与以外の手当や制度を充実させることも、会社の魅力を高める重要な戦略です。特に、お金に換えられない「働きやすさ」は、社員の定着に大きく影響します。
- 働き方の柔軟性:フレックスタイム制度やリモートワーク制度を導入し、育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整えましょう。
- 非金銭的なメリット:社員食堂や健康診断の充実、資格取得費用の全額補助など、社員の生活や成長をサポートする福利厚生を強化しましょう。
給与だけでなく、働きやすさを含めたトータルな待遇で他社との差をつけることが、人材確保につながります。
対策3:「生産性向上」とセットで賃上げを実現する
賃上げの原資(げんし)は、最終的には会社の利益から生み出す必要があります。そのため、賃上げを機に「社員の生産性を向上させる」取り組みをセットで行うことが重要です。
- 業務のムダをなくす:ITツールやRPA(ロボットによる業務自動化)を導入し、単純作業にかかる時間を減らしましょう。
- 成果を出すための教育:社員のスキルアップを目的とした研修や教育に投資し、一人ひとりがより高い成果を出せるように育成しましょう。
会社全体の利益が上がれば、無理なく高い水準の賃上げを継続できるようになります。
まとめ:賃上げ 中小企業は「戦略的な給与設計」が鍵
この記事では、大企業の賃上げ動向を踏まえ、中小企業がこの「賃上げ時代」を乗り切るための3つの対策をお伝えしました。
全員一律ではなくメリハリをつけること、福利厚生で魅力を高めること、そして生産性向上とセットで考えることが、経営を圧迫せずに優秀な人材を確保するための鍵となります。
「自社の給与制度にどうメリハリをつければいいか?」「賃上げに必要な生産性向上策についてアドバイスがほしい」――もし、そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。私たち当事務所では、貴社の体力と将来の成長を見据えた、戦略的な給与制度の設計や、社員教育制度の構築をサポートしています。人材を惹きつける強い会社づくりを、一緒に目指していきましょう。
参考資料