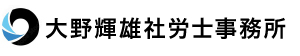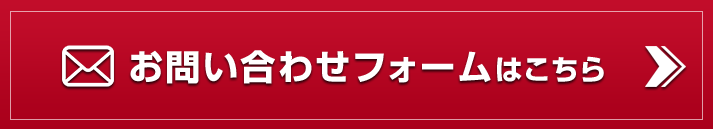「去年の5月に育児・介護休業法が改正されたのは知っているけど、具体的な対応はこれからでいいか…」
そう考えている経営者・人事担当者の方はいませんか?
改正法が施行され、介護離職防止のための「雇用環境整備」が義務化されて半年が経過しましたが、最新の調査結果は、多くの企業がこの重要課題への対応を先送りしている現状を明らかにしました。
マイナビの調査によると、義務化された雇用環境整備をまだ実施していない企業は36.9%にも上り、さらにその半数以上が「今後も実施予定がない」と回答しています。
制度が必要なことは理解しているものの、実質的な対応が進んでいないという、深刻な「意識と実態のギャップ」が浮き彫りになっています。
「制度はある」では不十分。進まない実質的な対応
調査では、「既に社内に介護に関する制度があり内容も充分」と回答した企業はわずか10%にとどまりました。その一方で、約半数の企業が「制度はあるが見直しが必要」または「制度が整備されておらず、早急に対策に取り組むべき」と認識しています。
これは、多くの企業が形式的な制度は整えていても、実際に社員が利用しやすい、あるいは安心して相談できる環境にはなっていないことを示しています。
介護は「いつ始まるか予測が難しい」「終わりが見えにくい」という面が大きいです。そのため、社員が「会社に迷惑をかけたくない」「キャリアを諦めたくない」という心理が働き、相談せずに離職してしまうというリスクを常に抱えています。
雇用環境の整備が進まないことは、以下の大きなリスクに直結します。
- 優秀な人材の突然の流出: 会社の屋台骨を支える中堅社員が、ある日突然、介護を理由に離職するリスクが高まります。
- 職場全体の生産性低下: 離職者が出た場合、残された社員に業務が集中し負担が増すことで、モチベーションが下がったり、さらなる離職を招く悪循環となることがあります。
- 法令遵守に関する問題: 法律に定められた義務を果たしていないことで、行政指導を受ける恐れやひいては企業イメージの低下につながるリスクを抱えます。
中小企業が今すぐ取り組むべき2つの環境整備
法改正で義務化された「雇用環境整備」は、決して大掛かりなものではありません。中小企業がまず取り組むべきは、以下の2点です。
1. 相談窓口の設置と情報提供
例えば「親が倒れたかもしれない」というような初期段階でも安心して相談できる窓口を設置することが第一歩です。
- 相談窓口の明確化: 担当する部署や担当者を明確にし、全社員に周知する。
- 研修・情報提供: 介護休業や短時間勤務制度など、法で定められた制度の内容を社員に周知するための研修や資料提供を行う。
2. 柔軟な働き方を実現する制度の見直し
介護と仕事の両立を可能にするには、時間や場所の制約を緩和することが有効です。
- 柔軟な短時間勤務制度の導入
- リモートワークの活用推進
- 年次有給休暇とは別に、介護のための特別休暇(有給・無給問わず)の検討
これは、自身の病気の時ほか、日常のあらゆる出来事に対応できる「社員の定着率向上策」でもあります。
介護離職ゼロへ。人事労務のプロとして御社をサポートします
介護は、誰にとっても他人事ではありません。少子高齢化が進む日本において、社員が安心して長く働き続けられる環境づくりは、企業の持続的な成長のための必須条件です。
私たちは、改正育児・介護休業法に対応するための「就業規則の改定」、社員の状況に合わせた「両立支援制度の設計」、そして社員の不安を取り除くための「相談窓口・情報提供体制の構築」をサポートします。
「制度があるだけ」で終わらせず、社員が「この会社なら安心して働ける」と思える、真の両立支援を一緒に実現しませんか?
参考:マイナビ:ビジネスケアラー支援実態調査結果 厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイント