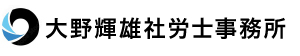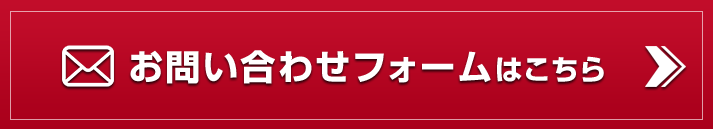「男性の育児休業」は、今や企業にとって重要な経営課題の一つです。
しかし「社員が育休を取ったら、誰が仕事をカバーするんだ?」という不安から、なかなか進まない会社も多いのが実情です。
そんな中、三井住友銀行が発表した新しい育休制度は、多くの企業の課題を解決するヒントを秘めています。
育休取得を「個人」の課題から「チーム」の課題へ
三井住友銀行は、2025年10月から男性行員の育児休業を「原則1カ月間必須」とします。
★ニュースリリースはこちら
『育休をきっかけとしたチームレジリエンス強化および男性社員の育休取得必須化の取組開始について』
しかもこれは単に育休の取得を義務付けるだけではありません。
- 報奨金の支給: 育休取得者本人だけでなく、業務をカバーした同僚にも1人5万円の報奨金を支給します。
この制度の核心は、育休を「チーム全体で支えるべきもの」と捉えている点にあります。
これまでは、育休取得者が「みんなに申し訳ない」と感じ、同僚が「負担が増えた」と感じるという、個人間の感情的な問題になりがちでした。
しかし、報奨金という形で会社がその貢献を評価することで、育休をチームで乗り越える前向きな期間へと変えようとしています。
取得率100%でも、平均取得日数が伸びない日本の課題
日本全体で男性育休の取得率は増加傾向にありますが、その多くは数日間の取得にとどまっています。
三井住友銀行も、2023年度には取得率100%を達成しながらも、平均取得日数はわずか12日でした。
今回、1カ月間の取得を「必須」としたのは、短期間の取得では、育児に夫婦間の協力体制を築くことや、当事者意識を持つのが難しいという現実を捉えたものです。
三井住友銀行の事例から学ぶ、中小企業の育休戦略
大企業である三井住友銀行の制度をそのまま真似するのは難しいかもしれません。
しかし、この事例から学ぶべき本質は、「育休をチームで支え合う文化をつくること」です。
あなたの会社でも、以下のようなことから始めることができます。
- 育休取得の目標設定: 育休の取得を「推奨」から「取得目標」へと一段階進める。
- 育休に向けてコミュニケーションの促進: 育休取得前から、チーム内で業務の引き継ぎやサポート体制について話し合う機会を設ける。
- 評価制度への反映: 育休中の業務カバーを「チームへの貢献」として正当に評価する。
育児と仕事の両立を支援する環境づくりは、社員の定着率を上げ、会社の魅力を高める重要な要素です。
御社の育休制度について、今一度見直してみませんか?